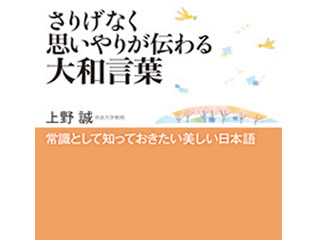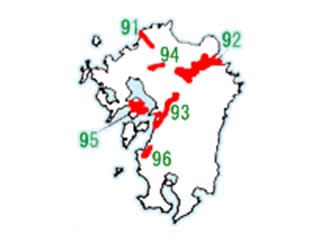大統領が職務停止中という異常事態の中、どうなることかと心配されていたリオ五輪だったが、多くの感動を残して無事終わった。 いろいろなところで感動ランキングが発表されていたが、それぞれにとってのベスト競技は何だっただろうか。
【私にとってのベスト競技】
1 .男子400mリレーの銀メダル
日本人の自己ベストは、桐生10秒01、山県10秒05、ケンブリッジ10秒10、飯塚は10秒22。 日本の五輪史上最強といわれている4人だが、世界レベルの9秒台は一人もいない。 日本はバトンパスに、下から差し上げるように行うアンダーハンドを採用し、渡す側と受ける側の双方がフォームを乱さず走ることを優先させ、世界が驚く夢の銀メダルを獲得した。
金メダルだったジャマイカのボルト選手は「予選から見ていたが、速いかもしれないと僕には分かっていた」「日本はチームワークがいい。この数年、彼らを見てきたが、彼らはいつもバトンの扱いが素晴らしい。我々よりはるかにたくさんの練習をしていて、チームメートを信頼しているのも分かる」と絶賛している。 さすがチームジャパンである。
2. 体操団体と内村選手の個人総合金メダル
体操の男子団体総合で、日本は2004年アテネ大会以来3大会ぶりに優勝した。 すべての種目に出場したエース内村は美しく安定感のある演技を見せ、19歳の白井も得意の床運動などで、G難度「リ・ジョンソン」、F難度「シライ2」、F難度の「シライ・ニュエン」とすべて成功させ、次のエースであることを印象付けた。
個人総合で内村選手は、最後の鉄棒で逆転し、史上4人目の2連覇を果たした。 「いい演技で一番いいメダルをとれた。 本当に一番の幸せ者です」と語る王者は、怪我などの試練を乗り越えてのひときわ輝く金メダルだ。
3. 錦織選手の96年ぶりの快挙銅メダル
準々決勝のモンフィス戦:
第1セットはタイブレークの末、錦織が先取するが、第2セットはモンフィスの力強いサーブ、粘り強いストロークに苦しみ、今大会初めてセットを失った。 最終3セットも再びタイブレークになり、モンフィスが先にマッチポイントを握るが、錦織が5連続ポイントで逆転勝利を挙げた。
ナダルとの3位決定戦:
第1セット、錦織は序盤から攻撃的な試合を行った。 第2セットで勝利を目前にしてからは、逆にミスが目立ち、このセットを落とした。 第3セットに入る前に2人はトイレ休憩をとったが、錦織のトイレ休憩が長かったため、観客からブーイングが出た。 錦織は気にするそぶりを見せず試合に集中したが、ナダルはプレーに粗さが目立ち始め、世界7位の錦織圭が、5位のナダルを6-2、6-7、6-3で下し、銅メダルを獲得した。 日本にとっては20年アントワープ大会の男子シングルスで熊谷一弥、同ダブルスで熊谷、柏尾誠一郎組が銀メダルを獲得して以来96年ぶりの快挙である。
4. 卓球女子(銅メダル) 男子(銀メダル)
5. 柔道吉田沙保里の銀メダル
【心打たれた競技】
1. 女子陸上5000m 予選での転倒
予選のレース中にニュージーランドのニッキ・ハンブリンが転倒し、後ろを走っていた米国のアビー・ダゴスティノが避けきれずに巻き込まれた。 先に立ち上がったダゴスティノがハンブリンを助け起こし、2人はレースを続行した。 あきらめずに完走した2人がゴール後に抱き合って互いをたたえた姿は世界中に感動の輪を広げた。
ハンブリンは「最初は何が起きたのか分からなかった。その後、肩に手を添えられて、これは五輪だからゴールしなきゃ、と言われた。これこそが五輪精神そのものだと思った」と語った。
2. 男子体操総合2位 ベルシャエフ選手のコメント
世界大会8連覇の内村に対し、海外メディアから 「あなたは審判に好かれているんじゃないですか?」という質問がでた。 内村は「まったくそんなことは思ってない。 みなさん公平にジャッジをしてもらっている」と答えた。 この質問に対し僅差で銀メダルになったベルニャエフは 「審判も個人のフィーリングは持っているだろうが、スコアに対してはフェアで神聖なもの。 航平さんはキャリアの中でいつも高い得点をとっている。それは無駄な質問だ」と心の深さを示した。
3. 難民選手10名の参加と国旗に変わる救命胴衣を思わせる色使いの旗
2020年に向けて 【同時通訳可能な翻訳アプリVoiceTra】
国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が提供している多言語音声翻訳アプリ「VoiceTra(ボイストラ)」が注目されている。 新バージョンでは29ヶ国語以上の文字翻訳・15カ国語以上の音声出力対応を行えるようになり、東京五輪に向けて話題になっている。 台湾華語、ウルドゥ語、ラーオ語等の文字翻訳にも対応するほか、ポルトガル語はブラジル方言にも対応するなど、きめ細やかな言語対応が行われていて、2020年までには、より精度の高いバージョンアップが行われる予定で、今から楽しみだ。
「VoiceTra」はGooglePlayやAppStoreで無料ダウンロードできるので、早速体験してみた。 日本中の英知を集めて東京五輪を成功させて欲しい。