












2013年1月 「ネット社会の可能性」

日経新聞に連載されている「ネット 人類 未来」は興味深い。 第3部の「山を動かす」では、グーグルがエネルギー問題などを解決するため、世界中の知恵を募る「Solve for X」というインターネット会議を最近発足させたという話題だ。 ネットの弊害も問題になっている昨今だが 「月面着陸級の大胆なアイデアを求む」というスケールにワクワクしその成り行きを期待してしまう。
最高経営責任者(CEO)のラリー・ペイジ(39)は「ネットという共通のインフラを使えば解決できないものはない」と話す。 英誌エコノミストの試算ではデジタル情報の蓄積量は世界の経済成長の4倍、コンピューターの演算能力は9倍の速さで増えているのだそうだ。
また、「データで食を救え」のテーマでは、畜産、メロン栽培 、気象予報などの各分野でデータを分析し、活用している例が示されている。
1月14日の関東地方の天気予報では、気象庁は雨予報を出したが、関東地方では10センチ前後の積雪となり正確な情報を伝えられなかった。 一方、民間の「ウェザーニュース」では正確に予報することができた。 その理由は、400万人のウェザーリポータの情報とレーダなど自社データを組み合わせ、気象データを解析し予報につなげるという、グローバル予報が正確な情報をもたらしたからだ。
「石油も千年間、枯渇せずにすむかもしれない」という「千年ゲーム」があるという。 ゴールはエネルギー問題の解決で、ネットで世界中から参加者を募り、節電のアイデアを投稿したり企画した節電の催しへの参加を呼びかけたりして内容が評価されればポイントがつくというものだ。プレー期間は一生で、プレーをするのは1年に1日。 そして、このゲームを人類が続ければ「石油も千年間、枯渇せずにすむかも」と言う。
ネットを通じてのゲームなど、したこともないがゲームという遊びの中でアイデアを出しているうちに世界中から知恵や膨大なデータが集まるのなら素晴らしいことだ。 この千年ゲームのひな型は、07年に米ゲームデザイナー、ケン・エクランドが開発したオンラインゲームで、石油がなくなった状況を想定して解決策を募ったものだという。参加者は石油が枯渇した後の生活シナリオをたて、動画などを投稿する。07年4月から32日間の期間中、12カ国から約2千人が参加したという。 ゲームを問題解決に使う取り組みは最近、「ゲーミフィケーション」と呼ばれ、効用を研究する動きが増えてきて注目されているという。
昨年の秋「バーチャル合唱団2000人の声」がNHKで放送され話題になった。 作曲家であり指揮者のエリック・ウィテカーの一人のファンの投稿動画がきっかけとなりに「バーチャル合唱団」が結成された。会ったこともない世界中の2000人もの人たちがネットを通じて連帯することで合唱は力強く素晴らしかった。「三人寄れば文殊の知恵」とはよく言ったものと思っていたが、ネットを通して無限のアイデアが集まれば、人類の未来は明るいかもしれない。
2013年2月 「団塊の世代」

2015年には団塊の世代が65歳に達し、日本は超高齢化社会へ進んでいるといわれている。
私たち団塊の世代の青春時代は、ミニスカートがはやりビートルズの来日にフィーバーする一方、ウーマンリブや学生運動などの波にもさらされた。 今振り返るとダイナミックな時代だったと思うが、それぞれがこれからの人生をどう生きていくかも問われている。
周りの団塊世代の人たちは、インターネットを自在に使いこなし、ブログやSNSでネットワークを広げている人も多い。 自分の寿命は神のみぞ知るで、一寸先の事はわからないが、これからもなるべく多くの人と関わっていきたいと思っている。
昨年、マンションの十一階から同じ敷地内で庭付きの一階に引っ越しをした。 庭といっても坪庭に様なものだが 「小さな果樹園」と示された巨峰が植えられていて、秋にはちいさいながら10房ほどの実をつけた。 小さくても巨峰は巨峰・・これからが楽しみだ。 そして、借景ながら、春には桜やハナミズキが、秋には紅葉がリビングから望める。 エントランスでは海棠やモクレンなど季節の花が出迎えてくれ、マンション生活にプラスされた自然の豊かさを味わうことができる。 こんなわが家を、みんなの集まる憩いの場に出来たらどんなにいいだろう。
2月6日に娘の第2子が生まれ、23日にはお相手がクリスチャンということもあり、息子が教会で結婚式を挙げた。 神父さまから「お互い、自分が相手を選んだのではなく、相手に選ばれたのだという思いを大切に・・」とのお言葉をいただいた。 「なるほど、人はどんな時も謙虚さと相手への思いやりの心が必要」と自戒の念を込めて思った。 教会の皆様のおかげで心温まるお式を挙げられ本当に感謝している。
自分の周りに人の輪がどんどん広がっていくのは、小躍りしたくなるぐらい嬉しいことだ。 長寿社会とはいえ、健康で長生きというのはなかなか難しい。 長生きすれば介護も認知症の問題も自分自身に降りかかってくるだろう。 そんな中でいつまでも希望を持ち続けられる人でありたいと願っている。
2013年3月 「さくらと宇宙」

例年にない寒さの厳しい冬が終わり、春の嵐が吹き荒れ、黄砂や煙霧に驚いているうちにも着実に春がやってきた。 今年の桜の開花は例年よりずいぶん早く、東京では16日に開花宣言が出された。 窓辺のカーテンをいっぱいに開くと、春のやさしい日差しが差し込んでくる。
3月の季語を見ると、山笑ふ・水温む・摘み草・蕨・土筆・・・と並ぶ。 孫と一緒に庭に下りると、こちらも孫の目線になり、ダンゴムシのユーモラスな動きに驚いたり、横浜では珍しい積雪に耐えた、ブドウの新芽にこころ躍らせている。 スギナも見つけた、はて、お友達の土筆は顔をのぞかせてくれるのだろうかと春を探すのも楽しい。
昨年末に引っ越した新居では(借景ながら)リビングに居ながらにして、桜を楽しむことができる。 花弁が風にそよぐ様を見ていると、実家にある八重桜の老木と亡き母の姿を思い出し、心がじんわりとしてくる。 母にこの景色を見せたら、さぞ喜んで一句詠んだことだろう。
毎年桜の季節になると、そわそわして落ち着かなくなりお花見に出かけるが、歩き疲れたり人の多さに圧倒されたり、思うように桜と対峙することができないことも多い。 我が家から眺める桜は、心静かに心豊かに楽しむことができ、プライベート空間を独り占めにするという贅沢を味わっている。
400年以上前の人間は、地球が宇宙の中心であり、人間は特別な天体に住む特別な存在だと信じていた。 しかし、今では地球と似た環境を持つ惑星は宇宙に限りになく存在し、この銀河系だけで少なくとも1億個はあるといわれている。 そんな宇宙の不思議に驚かされながらも、この地球に、この日本に、生まれてきた奇跡を味わっている。
2013年4月 「アメージング・グレース」

4月28日、息子の結婚式が横浜にある山手迎賓館で執り行われた。
お天気にも恵まれ、お祝いに集まってくださった方たちの笑顔もはじけて見える。
彼女がクリスチャンのため、教会での挙式はすでに終えていて、当日のチャペルでは司会者の進行で結婚の宣誓と指輪交換が行われた。 新婦の所属するゴスペルグループが参列者を両側から囲むようにたたずみ歌う「アメージング・グレース」「Oh Happy Day」に、あちこちから感声があがり、留袖を着ている私も思わずリズムに乗ってしまう。 心の奥底に響く素晴らしいお祝いの歌声だった。
披露宴会場に席を移した宴でもお祝いの言葉が続いた。 息子は学生時代所属していた混声合唱団の仲間と嵐の「One Love」をダンス付きで披露し、彼女はゴスペルの仲間と楽しげに「My life is in your hands」を歌ってくれた。 なんと素敵な仲間たちなのだろう。
産後すぐの娘家族も揃い、昨年秋に亡くなった母も写真で参加していた。 きっと笑顔で拍手を送ってくれていることだろう。 今までいろいろな方々に守られ支えられてきたことを親子ともども感謝しなければいけない。 宴を締めくくる感謝の言葉と共に若い二人から、生まれた時と同じ体重のテディーベアを送られた。 3,540gは何と嬉しく重いサプライズだ。 こちらこそ感謝!!感謝!! ほんとうに ありがとう。!!
そして今、グランドピアノの形をしたオルゴールで「アメージング・グレース」を聞いていると、宇宙の果てまで続くような不思議な空間を感じ、心が安らぎに包まれてくる。
2013年5月 「村上春樹」
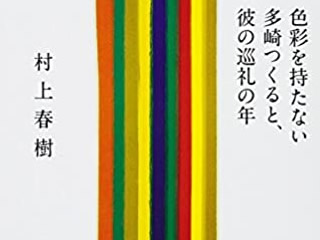
「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」は、発売後1週間で発行部数が100万部に達した村上春樹の小説だ。 予約してあった実物が手元に届いた後もなぜか暫く開かなかったのは、長編と聞いていたが意外と薄く、すぐに読んでしまうのが惜しい気がしたためだ。
主人公のつくる以外はそれぞれ、赤松慶(アカ) 青海悦夫(アオ) 白根柚木(シロ) 黒埜恵里(クロ)と名前に色彩の色が付いている高校時代の仲間だ。 その絆は、正五角形が長さの等しい五辺によって成立しているのと同じように必要不可欠と思われていたが、つくるは自分の名前だけに色がないことで一人疎外感を感じていた。
つくるは、大学進学を機に仲間と過ごした地を離れるが、その時を境に、仲間から縁を切られ無視されるようになり死をも考えるようになる。 社会人となったつくるは、恋人から「あなたはナイーブな傷つきやすい少年としてではなく、一人の自立したプロフェッショナルとして、過去と正面から向き合わなくてはいけない。 自分が見たいものを見るのではなく、見なくてはならないものを見るのよ。 そうしないとあなたはその重い荷物を抱えたまま、これからの先の人生を送ることになる。」と言われ、過去と向き合うため、仲間だった一人ひとりと会うための旅に出かける。 そして、明かされていく真実。
「あらゆる人間はこの生涯において何かひとつ、大事なものを探し求めているが、それを見つけることのできる人は多くない。 そしてもし運良くそれが見つかったとしても、実際に見つけられたものは、多くの場合致命的に損なわれてしまっている。 にもかかわらず、我々はそれを探し求め続けなくてはならない。 そうしなければ生きている意味そのものがなくなってしまうから」という作者の言葉が重く響いてくる。
2013年6月 「夢の人工光合成」

環境を破壊する「二酸化炭素」の削減が地球規模で緊急課題になっている。 その「二酸化炭素」と、どこにでもある「水」と「太陽光」のエネルギーで、燃料やプラスチックなどを作り出す夢の技術 「人工光合成」の研究が進んでいるという話が、NHKクローズアップ現代で紹介されていた。
植物は光エネルギーを利用して、水と二酸化炭素を合成し酸素を作り、同時に炭水化物を排出している。 その植物の働きを特殊な金属を使って再現し、光合成を人工的に行うという実験が進んでいるのだ。 人工光合成が実現したら、作った炭水化物から燃料となるエタノールを作ることもできる。 食料までも作ることが可能になれば、食料不足も解決してしまうという人類にとっては夢のような話だ。
二酸化炭素を人工光合成により有機物の燃料や食料に変えるという技術の発展は、1974年に世界最高の大型分析装置が兵庫県佐用郡に作られ、光合成の分析が可能になったからだという。 その大型放射光施設 SPring-8の蓄積リングは円形の加速器で周長1436mもあり、様々な研究に役立っている。 http://commune.spring8.or.jp/tour/
「人工光合成」はアメリカ・EU・中国・韓国も力を入れている。 アメリカは、人口光合成に5年間で100億円以上投じ、カリフォルニア州に人工光合成ジョイントセンターが作られ、130人の研究者が集まって研究をしている。 日本では2012年10月、ノーベル化学賞受賞の根岸英一氏の提言で、国家プロジェクトが立ち上げられた。
パナソニックでは、植物のように太陽光のエネルギーを使って二酸化炭素(CO2)と水からアルコールなどの有機物を生み出す「人工光合成」のテクノロジーを急速に進化させた。 今年に入ってエネルギーの変換効率が一けた向上、ついに植物並みのレベルに到達した、というからすごい。 また、トヨタでは高性能な三次元触媒を実現させたという。 2030年に変換効率を10%にする(植物は1%)目標を掲げ、日本は産学官の協働体制で脱石油革命をめざしている。 省資源国ながら日本の持つ技術の力はすごい!! がんばれニッポン!!
2013年7月 「京都の祖母」

母が亡くなってから9か月が経つが、母が過ごした京都での暮らしのエピソードや気丈だった祖母の姿が、母の声とともに蘇ってくる。 こんな日が来るならもっと色々な話を聞いておけばよかったと悔やみながら、母の書き残した冊子を読み、母と祖母のことを思う・・・。
祖母の教えの一つ目は「今日もお陰様で無事に過ごせました」という感謝の心と、日々の「ありがとう」の感謝の言葉だ。
二つ目は「何があってもあわてるな」の言葉。何時、 何事が起きてもお腹にぐっと力を入れ、こらえ慌てない。 祖母は、三男が戦死した時も、長男が出張中に心筋梗塞で倒れ帰らぬ人になった時も、お腹にぐっと力を入れてこらえたという。
三つ目は「何事もお互い様」の心。 祖母は、人の喜ぶ姿をみて喜び、人の世話に心を尽くし、周りの方や菩提寺のお坊さんから施しの人と言われていた。
京都は寺社が多く、毎日の生活の中にも仏教の教えが入り込んでいて季節ごとの伝統行事も多い。 お祭りや地蔵盆には娘たちに着物を着せ、ご馳走を作り、お客様の接待にあけくれていたという働き者の祖母は、縫い物や料理が得意で、人に振る舞うことが生きがいであったという。
母が入院することになった直前の春、母娘で祖母と父が眠る菩提寺の東本願寺さんを訪ね、母の友達とも再会する予定だったが、「やっぱり足が弱って旅行は大変そう」と取りやめになってしまった。 京都市中京区松原通御前角に、母が育った家はもう無い。 時間を見つけて母と祖母の思い出の場所をゆっくりと訪ねてみたいと思う。
2013年8月 「ITとひらめき」

メディアには毎日のようにIT、ネット、未来などの言葉が溢れている。
人にとって良いことなのか悪いことなのか、何だかいろいろな意味で境界線が混沌としている。
「MOOC」というアメリカで生まれた大学水準の大規模オンライン教育が、英語圏を中心に急速に広がり話題になっている。 登録している人たちの中には内戦で教育に恵まれなかった人や経済的な理由で留学がかなわなかった人も多いという。 有名教授の授業が無料で配信されれば、今まで教育の機会に恵まれなかった人々が恩恵を受け、教育の在り方も変わってくるだろう。 一方、英語での配信で、学問はますますアメリカ中心になっていくだろう。
「逆SEO」
「SEO」とは検索エンジンを最適化することで、故意に上位に表示させることが、以前問題にもなった。「逆SEO」とはその逆で、特定のサイトを検索結果の上位に表示させないように、順位を落とす細工をすることで、そういうビジネスがあるという。 確かに風評被害の対策ではあるけれど、いろいろなことが人為的に操作される時代になってきている。
最近、グループで担当しているホームページがハッキングされたのではないかと疑われる事件が起きた。 本当のことはまだわかっていないが、身近なところででも、ウィルスを始めいろいろな危険に晒されているのだと改めて思った。
最近読んだ新聞に「ひらめき」とは何か、という記事が出ていたが、大阪大学の情報通信研究機構では脳のひらめきの解明を行っているという。 ひらめきは人間の持つ直観的な能力だと思っていたが、ひらめきを解析するのはやっぱり科学の力。 脳細胞が少ない私は、なかなかついていけない。
2013年9月 「オリンピックと原発」

2020年夏季五輪とパラリンピックの東京開催が決まり、閉塞感の漂う日本に救世主が現れたかのような喜びが街にあふれた。 アジアの国で2度の開催は日本が初めてだという。
日本のプレゼンテーションに、今までにないチームワーク力を感じ、テレビにくぎ付けになった。 7年後の夢の舞台に心躍らせたが、福島の汚染水問題が改めて世界中の注目を集めた。 安倍総理は、五輪招致の演説と質疑応答で「健康問題は、今までも現在も将来も全く問題ない」「抜本解決へのプログラムを私が責任を持って決定し、実行していく」汚染水問題は「完全にコントロールされている」と断言した。
そんな中、7月に亡くなった事故当時の現場責任者である吉田昌郎・元福島第1原発所長の記事を読んだ。 吉田所長が亡くなってからは、事故の被害拡大を防いだ努力をたたえる意見が相次ぎ、 「日本を救った男」と英雄視された一方で、事故の責任者として責任を問う意見もあった。
吉田所長は、原子炉建屋の水素爆発で現場が騒然とするなか、突然、座禅を組み、瞑想を始めたという。 学生時代から仏教に興味を持ち、般若心経を学んでいたそうだ。 当時、現場にいた社員たちは「吉田所長の姿を見て動揺が静まった」という。 どういう思いだったのだろう。
かつて、東洋の魔女と呼ばれた日本の女子バレーボールの中継放送を修学旅行の電車の中で聞き、皆で盛り上がった。 優勝が決まった時の爆発的な感動は、今でも忘れることができない。 オリンピック開催は、子供たちに希望を与えるだけではなく、介護施設でもお年寄りに生きる目標を与えているという。 そんなオリンピックを祝うためにも、福島復興が早く実現することを心から願っている。
2013年10月 「野田山」

10月中旬、息子夫婦と先祖代々の墓所である、金沢の野田山を訪ねた。
金沢行は、本来お墓参りが目的だが、横浜からは遠路を訪ねることもあり、どうしても第二の要素である観光気分が強くなってしまう。
野田山は、加賀藩主前田利家の墓所を中心に家臣が周りを取り囲んでいるため、山全体が広大な墓地となっている。 藩主利家の墓は、土を盛り上げた土饅頭形式で、三段に盛り上げた方形墳の周りを方形の溝がめぐるという独特の形態を採り、一辺約19メートルと、他藩では類を見ない大規模なものである。
小松空港から金沢に向かう途中で見た日本海の荒々しさは、時々訪ねる鎌倉の穏やかな海とはまるで異なり、北朝鮮の拉致問題を思い起こさせた。 帰ってからも気になり、蓮池薫さんの「拉致と決断」を読んだ。
拉致により、突然人生を変えられた蓮池さんの過酷な状況と、生きるための判断と家族を守るために考え抜いた決断が胸に迫ってくる。 翻訳業をしていたので鍛えられたという文章力も素晴らしい。 日本への帰国が決まるその瞬間まで、北朝鮮で一生暮らさなければいけないという、悲壮な覚悟で生きてきたことが伝わってくる。 日本の報道ではなかなか伝わってこない北朝鮮の人々の日常生活や指導者に対する気持ちが書かれていて、北朝鮮のことを知る手掛かりにもなった。
今回はお墓参りの後、近江町市場や兼六園を訪れ和倉温泉の奥座敷に佇む多田屋で能登湾の幸をいただき、景色を堪能することが出来た。 平和な旅になったことに感謝している。
2013年11月 「京都」

「そうだ 京都、 行こう」のコマーシャルが始まって今年で20年になるという。
今年の秋は南禅寺天授庵だった。いつもその魅力あふれる映像と語り口に魅了されているが、撮影監督(高崎勝二)、キャッチコピー(太田恵美)、ナレーション(長塚京三)曲(My Favorite Things)は20年間ずっと同じだったと知り、改めてすごいと思った。
まだ観光客が少ない11月のはじめ、紅葉がようやく色付き始めた京都を訪ねた。
一日目は、山城高雄の神護寺・槙ノ尾の西明寺・栂ノ尾の高山寺・・
二日目は、東本願寺・天竜寺・常寂光寺・落柿舎・二尊院・祇王寺・大覚寺・・
三日目は、源光庵・光悦寺・大徳寺・清水寺・高台寺・建仁寺・・
紅葉は1分から8分というところでフルシーズンにはない繊細な紅葉を楽しみ、靴がつぶれるほど歩き回り、観光シーズン前の京都を堪能した。 特に印象に残ったのは、源光庵と光悦寺だ。
丸い「悟りの窓」と四角い「迷いの窓」のある源光庵は、「私は宇宙を、友人は人生を、考えていたのでした」で知られている曹洞宗の禅寺で、是非訪ねたいお寺だった。 早朝は観光客が一人もおらずひっそりとしており、「悟りの窓」と「迷いの窓」の2つの空間と時間を独り占めすることが出来た。 他に人がいないことを幸いに、部屋の横にある幅の狭い濡れ縁の先からお庭を眺めてみた。 部屋の中からそれぞれの窓を通してみたのとは印象が異なり、禅寺の枯山水というよりも、穏やかで優しいお庭だった。 さらに、濡れ縁を進み、今度はそれぞれの窓の外から内側のお部屋を眺めてみた。そこにはなんとも静かなふんわりとした雰囲気のお部屋が佇み、「悟り」も「迷い」も心の持ちかた次第で、本当は紙一重ではないか、との印象を受けた。 これは予期せぬ事で、人間の生涯を表す「生老病死」を象徴する「迷いの窓」とも、もうしばらく付き合っていくのも悪くない、と思えた瞬間だった。
本阿弥光悦が工芸集落を営んだという光悦寺では、数日後から開かれる茶席の準備が進められていたが、鷹峰三山を背景にしたお庭の紅葉は、繊細で素晴らしいものだった。 後で聞いた話では、この茶席はお茶を振舞うのではなく、お道具を拝見する茶会だそうだ。 風景の中にお茶室が点在する静かな庵で、お茶をいただけたら「生老病死」も忘れ、心穏やかな至福の時が過ごせることだろう。
さて、今年の「そうだ 京都、 行こう」のキャッチフレーズは
済々年々 人同じからず。 来るたびに感じることが違う。
今年の紅葉を 今年の私が見て さて 何を思うでありましょう。
「今年の紅葉」を見に行く、と言いながら
「今年の自分」を見に行く私、でもありました。
京の魅力は尽きない。 祖先の暮らしたこの町で旅人としてではなく、ひっそり暮らしてみたいものだ。
2013年12月 「2013年」
 今年はアベノミクスで始まり、消費者の“心のデフレ”も和らぎ、年末商戦でも高額商品が売れているという。 6月に富士山が世界文化遺産登録され、9月に2020年東京オリンピック・パラリンピックが決定した時は、皆が7年後の自分に思いをはせた。 12月には日本食が無形文化遺産に登録されるなど、今年はいつになく、明るい話題が多かったように思う。
今年はアベノミクスで始まり、消費者の“心のデフレ”も和らぎ、年末商戦でも高額商品が売れているという。 6月に富士山が世界文化遺産登録され、9月に2020年東京オリンピック・パラリンピックが決定した時は、皆が7年後の自分に思いをはせた。 12月には日本食が無形文化遺産に登録されるなど、今年はいつになく、明るい話題が多かったように思う。
そんな中で、12月5日、ネルソンマンデラ南ア元大統領の死去のニュースが世界中を駆け巡った。私が元大統領を知ったのは、映画「インビクタス/負けざる者たち」を見てからだと思う。 マンデラが繰り返す「我が運命を決めるのは我なり、我が魂を制するのは我なり」は、英国の詩人ウィリアム・アーネスト・ヘンリーの詩の一節とのことだが、どんな運命にも負けない不屈の精神は、元大統領の人生そのものを現していた。
10日の追悼式にはオバマ大統領やバン・キムン国連事務総長も参列し、元大統領の功績をたたえた。その弔辞を聞くにつれ、改めて大きな宝を失ったことを心から残念に思った。 オバマ大統領は「彼に影響を受けた世界中の人々は、哀悼の意を表し、英雄の生涯を祝福する時だ。歴史上の巨人だった。国家を正義に導き、世界中の何十億の人々を揺り動かした」と讃え、国連事務総長は「許容することの偉大な力を示し、真の平和で人々を結びつけた。身をもって教えてくれる偉大な教師だった。自由、平等、民主主義、そして正義のために多大の犠牲を払った」と語った。 こんなに人々に影響を与え、惜しまれる方はなかなか現れないだろう。
今年は、息子が元旦に入籍・4月に挙式し、2月には娘が第二子を出産し我が家でも明るい話題が続いた。 さて、来年はどんな年になるのだろう。 「過去もその時点では現在なのだ」という言葉をかみしめ、その時々を大切にしていきたい。





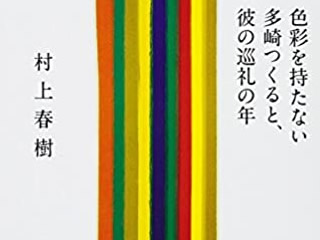






 今年はアベノミクスで始まり、消費者の“心のデフレ”も和らぎ、年末商戦でも高額商品が売れているという。 6月に富士山が世界文化遺産登録され、9月に2020年東京オリンピック・パラリンピックが決定した時は、皆が7年後の自分に思いをはせた。 12月には日本食が無形文化遺産に登録されるなど、今年はいつになく、明るい話題が多かったように思う。
今年はアベノミクスで始まり、消費者の“心のデフレ”も和らぎ、年末商戦でも高額商品が売れているという。 6月に富士山が世界文化遺産登録され、9月に2020年東京オリンピック・パラリンピックが決定した時は、皆が7年後の自分に思いをはせた。 12月には日本食が無形文化遺産に登録されるなど、今年はいつになく、明るい話題が多かったように思う。