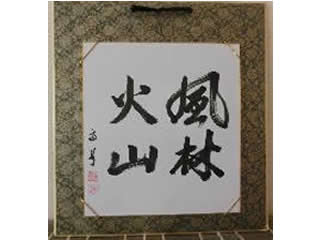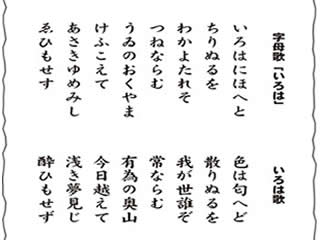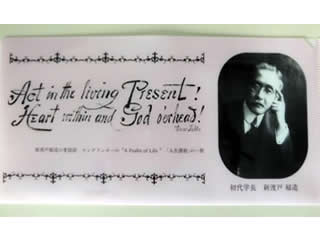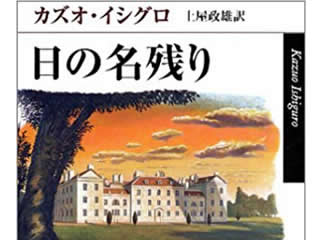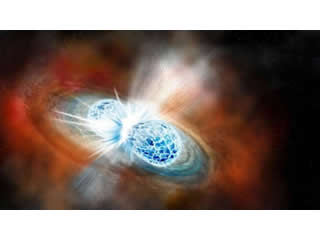元旦の新聞に「破壊と創造の500年」という特集記事があった。
イギリスがEUを離脱し、アメリカではトランプ大統領が誕生した。 これから世界はどこに向かうのかと不安になる中、過去への振り返りと未来を見据える記事が続いた。
この500年は、コロンブスの大航海時代から始まり、ワットらによる第1次産業革命、フォードやエジソンによる第2次産業革命と明治維新、スティーブン・ジョブスやビル・ビルゲイツ、ザッカー-バーグらによるデジタル第3次革命を経て第4次革命へとつながっていく。
21日にアメリカ大統領に就任したトランプは人事から外交まで重要な政策はツイッターで発信し、記者会見を嫌う。 外交問題ですらツイートし、その情報は瞬く間に世界中に広がっていく。 ニュースは広くネット上で発信されているが、偽情報も氾濫している。 国家間の意図的な情報操作もある一方、小遣い稼ぎの若者がツイッターの広告料を目当てにセンセーショナルなデマ情報を流している。 個人の情報選択能力が問われ、うかうかしていられない。
人工知能やIoTがもたらす第4次産業革命によって、未来はどうなるのだろうか。 かつての製造業は、安い人件費の国を求めては彷徨っていたが、産業用ロボットやIoTの活用で、日本が得意とするモノづくりの現場にも新しい波が押し寄せている。
先日、ビットコインの記事を読み驚いた。 「ビットコイン VS 銀行 22世紀のカタチ そこに」という記事である。 三菱UFJフィナンシャル・グループが今年度中にも、独自の仮想通貨「MUFGコイン」を発行するという。 ギリシャでは、政府も中央銀行も信頼が薄らぎ、金融資産の2割をビットコインが占めるという。 米のバンク・オブ・アメリカでは「グローバルに金融業から2500万人分の職が消える」として「大量失業時代」の到来を予測している。
人が人類として進化したのは認知機能であり、貨幣と言語の起源は人類の認知機能の進化だといわれている。 人類進化論的に言うならば、目に見えない仮想通貨のビットコインは、ますます広まっていくことになる。 初期のビットコインをめぐるトラブルをみて、仮想通貨なんてそのうち消えてなくのではと思っていたが、10年先にはどうなっているのだろう。
お正月の箱根駅伝をインターネット無料サービスの「スカイプ」を使って、ロンドンの息子家族に生中継した。 走るという究極のアナログを、離れたロンドンにリアルタイムで中継できるなんて、やはり技術進化の賜物である。