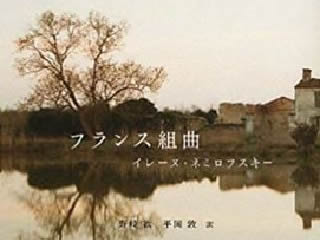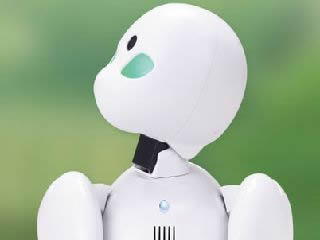寒気がするけどこのぐらいは大丈夫と思っていたのに、インフルエンザにかかってしまった。 たかがインフルエンザされどインフルエンザ。 久々のインフルエンザは手ごわく、今年は最悪のペースで感染が広がっているとニュースでも伝えられている。ウィルスにやられて寝込んでいる時、「人類が滅びるとしたら原因は何だと思う。 ウィルスによる、核戦争による、隕石の衝突による…」 という、40年以上も前の友の質問を思い出した。 ウィルスや核戦争は人類の英知で何とか防げるのではないかと思い 「隕石だと思う」 と答えた気がする。
寒気がするけどこのぐらいは大丈夫と思っていたのに、インフルエンザにかかってしまった。 たかがインフルエンザされどインフルエンザ。 久々のインフルエンザは手ごわく、今年は最悪のペースで感染が広がっているとニュースでも伝えられている。ウィルスにやられて寝込んでいる時、「人類が滅びるとしたら原因は何だと思う。 ウィルスによる、核戦争による、隕石の衝突による…」 という、40年以上も前の友の質問を思い出した。 ウィルスや核戦争は人類の英知で何とか防げるのではないかと思い 「隕石だと思う」 と答えた気がする。
改めて調べてみると 「太陽の死」 「ポールシフト」 「土星爆発」 「スーパーボルケーノの噴火」 「小惑星の衝突」「全面核戦争」 「スーパーウィルス」 「AIの暴走」 「氷河期」などなど・・・新しい不安要素が加わっている。 太陽の死まではあと50億年、地磁気逆転が数十万年ごとに起こるポールシフト、爆発力は原爆の1000倍以上といわれる米の巨大火山「イエローストーン」の噴火と続く・・・。
昨日、世界終末時計のことが報じられていた。 世界終末時計は、核戦争などによる人類の終末を午前0時にたとえ、その終末までの残り時間を 「あと何分」 という形で象徴的に示す時計である。 オブジェはシカゴ大学にあるが、実際の時計ではなく時計の45分から正時までの部分を表している。
終末時計は、日本への原子爆弾投下から2年後、冷戦時代初期の1947年にアメリカの科学誌 「原子力科学者会報」 Bulletin of the Atomic Scientists の表紙絵として誕生したものである。 未来の世代のために時計の針を戻し、世界をより安全なものにしようという市民活動のサイト 「 TurnBackTheClock.org」 が設立されている。
トランプ大統領が核廃絶や気候変動対策に対して消極的な発言をした昨年は、残り時間は2分30秒前まで縮まり、 北朝鮮の核・ミサイル開発により朝鮮半島での危機が増したため、今年に入り、さらに30秒進み残りわずか2分となった。 これは、冷戦期で核戦争の脅威が高まった1953年の残り2分と並び、過去最短となる。
そんな世の中の邪気を払いたく、今年は少し早めにお雛様を飾った。 すると、いつのも日常の空間がパーッと華やいだ。 女の子の健やかな成長を願うひな祭りだが、お雛様の両脇には左近の桜・右近の橘が飾られる。
桜と橘は、京都御所に存在する紫宸殿に由来するもので、御所内では親王様から見て紫宸殿東側に桜、西側には橘が植樹されている。
桜と橘には、古来から「魔除け」「邪気払い」の力があると考えられていて、橘には「不老長寿」を願う役割もあるとされる。 お雛様でよく飾る桃の花は桜の代用で、桃にも邪気払いの霊力が強く備わっているためと考えられている。 人の英知を信じ、何時までも穏やかにひな祭りを迎えたい!!と願っている。
If winter comes, can spring be far behind ? 冬来たりなば 春遠からじ